教員が出産したらいくらもらえるの?
産休に入って調べた出産に関わるお金のあれこれ。教員じゃなくてももらえるもの、教員だからもらえるもの全部ひっくるめて「公立小学校教諭」の私がいくらもらえたのかをまとめました。金額などは2024年7月に出産した私の例になります。地域によっても異なるかもしれませんし、現在は見直されているものもありますので、あくまでもご参考に。
出産育児一時金(出産子育て応援給付金) 10万円
私の住む自治体では妊娠時に5万円、出産時に5万円と分けて支給されました。妊娠が確定して母子健康手帳をもらいに行ったときに保健師さんと面談をし、1回目の申請を行いました。出産後は保健師さんの訪問面談があり、その際に2回目の申請をしました。受け取りはどちらも自分が指定した銀行口座にお金を振り込んでもらうという方法でした。
出産育児一時金 50万円
私は公立小学校の教員なので、出産費という名目で公立学校共済組合から支払われました。請求方法には直接支払制度・産後申請方式・受取代理制度の3つ選択肢があります。私の場合、出産費用(入院費込み)が50万円を超えていましたが、産院が申請を代行してくれる直接支払制度を選択していたため退院時には一時金との差額分だけを産院に支払いました。50万円を下回る場合は逆にその差額分を受け取ることができるそうです。
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
出産費付加金 5万円
公務員には付加給付というものがあり、公立学校共済組合から出産一時金が支払われると追加で出産費付加金5万円が給与口座に振り込まれました。ありがたいことです。
産休中のお給料 毎月の給与額+ボーナス
公務員の場合は産休手当(出産手当金)ではなく、産前産後の各56日間は今まで通りのお給料がもらえます。私は帝王切開で予定日よりも出産が早まりましたが、予定日を基準として56日間と計算され、56日目が属する月は日割りで計算された額が支給されました。産休中の短期共済掛金(健康保険料)と長期掛金(年金保険料)は免除となるため、産前休暇中のお給料から引かれていた掛金は出産後に返還されました。これらの手続きはすべて産休に入る前に書類を事務へ提出しておいたので、事務の方が手続きを進めてくれました。
ボーナスについてですが、産休に入ってから1回目の6月は満額(5月途中までは出勤、その後は産休中のお給料も出ていたため)、2回目の12月は産前産後休暇中の給与が出ていたためその期間分のボーナスが支給されました。感覚的には「仕事もしていないのにこんなにもらえるなんて!」という感じで、教員であることの有難さを実感しました。
育児休業手当金
子どもが1歳に達する日まで共済組合から給付されます。育児休業開始日から休業日数が通算して180日に達するまでの期間は標準報酬日額の67%が、181日目からは50%が休業日数分支給されます。(ただし給付上限額があり、その額は毎年見直されます。)支給額は事務の方が毎月送ってくれる給付金決定通知書で知ることができます。標準報酬日額をどこで調べればよいかがわかりませんでしたが、ネットの情報や自分の給付金決定通知書から計算して確かめたところ給与明細に書かれた標準報酬月額÷22で計算される額になっていました。
子どもが1歳になるともらえなくなる育休手当ですが、「手当支給の延長要件」に該当する場合は最長2歳に達する日まで支給を延長してもらうことができます。そのためには子どもが1歳に達するまでに保育所入所の申し込み手続きをしなくてはなりません。(入所希望日は1歳の誕生日まで)これを忘れるとその後に延長申請をしても支給はされなくなります。2025年4月からは支給要件が少し厳しくなり、待機通知に加えて保育園の申込書の写しも提出が必要になりました。自治体ごとに申し込み書の様式も異なるため詳細についてはお住まいの自治体や共済組合などに要確認です。
我が家は利用していませんがパパママ育休プラスの制度を使えば育休手当のもらえる期間を延長できたり、金額も多くもらえるようですね。
児童手当 1万5000円
3歳未満(一律) 15000円
3歳以上小学校修了前 10000円(第3子以降は15000円)
中学生 10000円
所得によっては特例給付の5000円が支給されるようです
調べていて少し混乱したのは請求の方法です。児童手当はパパママのうち前年の収入が高かった方が受給するのが基本です。出生日の翌日から15日以内に現住所のある市町村に申請するのですが、公務員は市町村ではなく所属庁に申請しなければなりません。つまり職場の事務の方に書類を提出して申請するということです。妊娠中に読んでいた雑誌の情報で「出生届」「こどもの医療費助成」「児童手当」の手続きは産後初のパパの仕事と考えていたのですが、民間勤めの夫より収入の多い私が児童手当の申請をしなければいけないことが分かり、産休に入ってから事務の方に書類を送ってもらうことになりました。ちなみに申請期限を過ぎてしまった分の手当はもらえなくなるので、なるべく早く提出するよう事務の方から言われた記憶があります。
扶養手当(家族手当) 1万円
子どもの扶養についても混乱しました。当初は「育休中の扶養手当が出ないなら夫の扶養に入れよう。」と話していました。しかし先ほど書いたように収入の多い私が児童手当を受給しなければならないとわかり、混乱した私は健康保険(子の扶養)についても同じなのだと勘違いして自分の扶養に入れてしまいました。(児童手当とは関係なく、扶養はどちらの親でもOKです。)産後休暇中は給料が支払われるため月1万円の扶養手当も出ていましたが、育休に切り替わると扶養手当は出ません。どちらの扶養に入れるかについては、今後の働き方やお互いの勤め先の制度を調べてから決めた方が良いです。
扶養といっても上記のような「社会保険上の扶養」と、もう一つ「税制上の扶養」があるようです。「税制上の扶養」は年末調整で記入する扶養親族のイメージです。出産した2024年は私にもまだ給与収入(給与所得)がありましたが、今年はそれがありません。育休手当は給付であり所得とは見なされないため、今年は夫の「税制上の扶養」に入れるということかと思います。そうなると夫は配偶者控除が受けられるので2025の年末調整でやってみようと考えています。
乳幼児の医療費助成
住んでいる自治体が生まれた子どもの医療費の一部または全額を助成してくる制度です。出生届を出すときに申請することで受給者証が郵送されてきました。「1回の負担額は500円まで」の自治体に住む私の子どもが、高熱で夜間休日診療にかかったときの領収書には7000円超の医療費が書かれていましたが、実際に支払ったのは本当に500円だけでした。子どもは怪我や病気が多いので医療費の負担を軽くしてもらえるのは助かります。
出産見舞金 4万円
教職員互助組合から給付されました。私の場合は上記の公立学校共済組合による出産費付加金の給付が決定すると自動給付となり、特に請求の手続きはしませんでした。共済組合の給付金振込の翌月に給与受け取りをしている銀行口座に振り込まれました。
親睦会より
職場の親睦会に入っていたので、そちらからもお祝いとして5000円をいただきました。
その他
公立学校共済組合より
出産一時金・出産費付加金に加えてベビー用品配布事業としてカタログギフトが届きました。プレゼントの中から1つ選ぶのですが私は5000円相当の積み木をいただきました。
教職員互助組合より
出産見舞金に加えてベビー用品購入補助券として、ミキハウスやコンビのオンラインショップで使える5000円分のオンラインチケットをいただきました。
掛金免除について
もらうというより実質的に助かるという意味で書いておきます。共済組合・互助組合ともに産休・育休中の掛け金は免除されます。ちなみに私は教職員組合にも入っていますが、給与明細を見ると産休中も組合費は引かれていました。育休に切り替わってからは特に支払いはしていないので免除になるのかと思います。名前がややこしいですが、教職員共済(総合保険や生命保険、医療保険、車の保険など)は保険なので、当然ですが育休中であっても掛金免除にはなりません。
おわりに
初めての出産でいろいろと気になるお金のことですが、あれこれ調べるのは少し大変だったのでここに私の経験をまとめてみました。どこかで同じように気になっている先生の参考になれば嬉しいです。


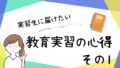
コメント